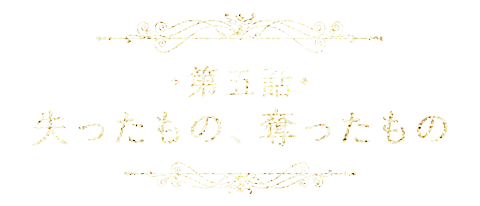
乾いた風が頬を撫で、長い黒髪と夜闇のように深く暗い蒼色のローブを揺らしていた。
王城の中にいた時には分からなかった、外の風。
土と石、鉄と血。
戦場の匂いはそれが錯覚なのだと理解していても、リリスにまとわりついてくるように感じられた。
人が死ぬ。
人を殺す。
それは、父親を殺した時には感じなかった胸を締め付けられるような感覚だった。
それを感じると、父親よりも他人に心を許しているかのように感じられて、リリスは自嘲してしまう。
それを親不孝と笑うのか。
それとも、自分にまだ感情が残っているのだと呆れるのか。
視界の先で、土煙が上がっている。
ここは、戦場の最前線。
今も目の前で、リリスの指示に従う兵士達が敵兵を倒し、そして敵兵に倒されている。
……兄は、シヤウンは、このような場所に居たのか。
そう思うと、それほど時間が経っていないはずなのに、とても懐かしい気持になった。
「どうかなさいましたか、リリス女王様」
「いいえ。なんでもないわ」
リリスが父王を殺害してから二週間の時が過ぎていた。
あの凶事から半日も経たないうちに、リリスは前王を、戦争を不要に長引かせて私腹を肥やした悪逆の徒として国民に伝えた。
時は金なり、人生は有限なり。
王殺しという凶事の場から逃げ出した貴族たちがリリスを国王殺しの大罪人と宣言するよりも早く行動したことで、リリスは少なくとも国民から敵意を抱かれることはなくなった。
そして、前王とともに私腹を肥やした貴族たちの名前を一人ずつ上げ、国王殺しの汚名から国民の目を逸らすことに成功していた。
同時に、国民から愛されていたシヤウンの死に前王が関わっていたことも伝え、同情も誘う。
戦争で家族を失った者、長引く戦争で生活が困窮する者、下世話だが――リリスの美貌に惹かれる者。
彼らは王が死んだ悲しみよりも、戦争を不要に煽り、長引かせたことに対する憎しみを抱いてリリスを支持した。
彼女が優れていたのは、それと同時に次の国王として前王に支持されていたtabaiを玉座に据えたことだろう。
Tabaiは正統な次の王である。
カイオス王国は光と闇の血脈が交互に王座に就く決まりがあり、前王は闇、そしてtabaiは光の血脈――その血脈に問題はなく、リリスの迅速な行動に動揺した貴族の内に僅かだがリリス側に付く人物もいた。
所詮、時勢に迷い、リリス側に旨味があるかもと思った連中だ。
心から信頼はできないが、貴族『全部』を敵に回すよりは遥かにマシである。
リリスは正統な血族と一部の貴族、シヤウンを支持していた軍部、大多数の国民からの支持を得て反乱軍――前王に義理立てするのではなく、自分の悪徳を隠すためにリリスを『王殺しの魔女』と断じた連中に刃を向けた。
カイオス王国内の内乱である。
当然、その混乱に隣国のオルダー公国が便乗しないはずもなく、今、カイオス王国は外からはオルダー公国、内からは貴族率いる反乱軍という二面攻勢に晒されていた。
だが、リリスをはじめ、王国軍に悲観の色はない。
それは――リリスに優れた軍を操る才能があり。
文字通り彼女は『魔女』だったからだ。
彼女はまるで戦場を俯瞰するかのように認識し、軍を駒のように扱った。
時に正面から、時に搦め手で。地形を利用し、人心を理解し、勝利すれば退却し、劣勢になれば攻める。
今までの常道から外れた戦略は、エスタリアの大地に新しい戦争をもたらしつつあった。
いまも早馬が矢継ぎ早にリリスの元に届き、『蒼の魔女』は戦況にあった策を授けていく。
そこに迷いはない。
指揮官の迷いは兵に伝播する。
ならばリリスは『魔女』として、傲岸に、不遜に、絶対の勝利を疑わない意思のこもった声で指示を出す。
それが兵を勇気づけるということを理解しているから。
「特別なことはしていないのだけれどね」
「そうなのですか?」
あの老人が現れてから自分の人生が変わったのか、それともこうなる運命だったのか……リリスは考える。
そんなリリスの傍に控えるのは、燃え盛る炎のように煌めく赤髪の少女、リース。
リリスは、この赤い少女だけを傍に置いた。
他は誰も信頼できないからだ。
兄が、シヤウンがリリスに似ていると、悪意を感じないと言っていた少女だけを、リリスは信頼していた。
「今となっては、一番信頼できるのが貴女だけだなんてね」
「ありがとうございます」
「褒めていないわ――自分の人生に呆れているだけよ」
そう言って、リリスは戦場を冷めた目で見る。
人が死んでいく。
死んだ人は、生き返らない。
当たり前のことなのに、人が人と殺し合っているこの戦場に……感情が沸かない。
殺したいのは兄の死に関わった貴族達。
けれど、そこへ辿り着く為にはたくさんの兵士を殺さなければならない。
……殺したくないと弱音を吐けば、リースはどう思うだろうか。
リリスは一瞬そう考えたが、今更どうにかできるはずもない。
「それも、どうでもいいこと……か」
「何か?」
その呟きを聞き逃したリースがリリスを見上げ、彼女は何でもないと首を横に振る。
リリスにとって、この戦いで重要なのは兄シヤウンを殺した貴族達を誅すること。
その後、この国がどうなろうが知ったことではない。
もう、そこまで面倒は見ない。
知ったことかと吐き捨てる。
彼女の中から、零れ落ちていく。
兄との約束が。兄との思い出が。
日が経つごとに零れ落ち、無くなっていく。
残るのは、自分でも御しきれない……冷たく、暗い、燻る炎。
敵も味方もなく、使える駒を使って倒すべき悪を追い詰めていく――ただそれだけ。
貴族の反乱軍も、隣国のオルダー公国も。
クツ、と。
リリスが低く笑い、その横顔をリースはじっと眺めていた。
見たもの全員が恐ろしいと感じるだろうその横顔を、しかしリースは、悲しそうだと感じる。二週間前からずっと、リリスは悲しそうだ、と。
少女が思い出すのは、自分とリリスが似ているといったシヤウンの明るい声だ。
そして、その青年を『家族』だと言った時のリリスの花のようにほころんだ表情だ。
同時に、提灯者モンの言葉も思い出す――歴史に干渉するな、という言葉。
リースが彼と出会い、彼が間違ったことを言ったことは一度もない。
ならきっと、リリスは間違えているのだろうと思い――それでも止めない。
『家族』がなくなって悲しいことを、よく知っているから。
「リリス女王様、」
リースがリリスの名前を呼ぶのと同時に、遠くから喧噪が聞こえてきた。
聞き覚えのある声は、tabaiだ。
彼は時折前線に現れては、兵士たちに無理難題を押し付ける。
自分がリリスよりも優れていると証明するために、自国の兵士を無駄に消耗させていく。
この戦争に勝利した後、リリスよりも優位に立つために。
何を以て優位とするのか――そう考えると、リリスは笑うよりも気持ちがより一層冷たくなるのを自覚する。
そういうところが暗愚なのだと思い、けれどもそれがこの国の王の姿であるのだとも思う。
リリスはため息をつき、tabaiの好きにさせる。
反乱軍を滅ぼすまでの我慢だ――ここで苦言を呈しても真意は伝わらず、tabaiは一層反発するのだと、簡単に想像がつく。
「少し出てくるわ」
「わかりました」
きっとtabaiはリリスの元にも来るだろう。
そして言うのだ。
まだ反乱軍の討伐は完了しないのか。
オルダー公国には攻め込まないのか、と。
この内乱が終われば、次は我が身だと気づかないまま――そんな下らない問答に時間を割くくらいなら、自陣を見回ったほうが有意義だとリリスは散歩をするような足取りで歩く。
傷ついている兵士は、そう多くない。
反乱軍の士気は高いが、まだ本格的な攻勢には出ていないからだ。
まずは敵を弱らせる――街道に検問を設置して物流を滞らせ、田畑の稲を刈り、山の一部を焼いて食糧が手に入らない状況にし、飢えさせている。
今はまだ開戦前に蓄えた食料が残っているだろうが、ひと月と持たないだろうとリリスは予想している。
貴族は大食いだ。
戦時中だと理解せずに、腹を満たす。
それで足らなくなれば兵士から食料を徴収し、それが無くなって、ようやく追い詰められているのだと気づくのだ。
……考えながら歩いていると、陣内の一角に目が留まった。
前線の陣にありながら、子供の姿があったからだ。
子供が、泣いていた。
前線の喧騒に飲み込まれる、小さな声で。
……血だまりに沈む、母親の手を握りながら。
「そういえば、先日……」
Tabaiの指示でオルダー公国側の砦を一つ、攻めたのを思い出す。
周囲を見回すと、土と血で汚れたオルダー公国の国旗が視界に映る。
早く砦を落とすように急かされての行軍だった。
小さな砦だったが兵士に負傷者が出たという報告を受けていたのを思い出す……その砦から流れてきた難民だろうか。
周囲には他にも老人や子供たちの姿がある。
ただ、その血だまりに沈む女性だけは、難民にしては着ている服が高価だった。
――傷が深い。
もう助からないというのは、誰の目にも明らかだ。
だからカイオスの兵士たちも、同郷の難民たちも、何もしない。
今にも息絶えそうな女性と、泣きじゃくる少女を遠巻きに眺めているだけ。
戦争の光景。
所詮は他国の住人で、他人よりも縁遠い存在。
そんな死に至る女性を眺めていると、少女が、リリスを見た。
……いや、睨みつけたという表現が正しいか。
リリスが気になったのはその瞳だ。
瞳の色が左右で異なっている少女――オッドアイやヘテロクロミアと呼ばれる、虹彩異色の瞳。
「お母様――ああ、ああ――お母様っ」
だがすぐに、少女は母親の胸に顔を埋める。
……ああ、死んだのか。
戦争に巻き込まれて。
自分が起こした戦争に巻き込まれて。
ただ漠然と、リリスはそう思った。
少しだけ、胸の奥がざわつく。
リリスは手で胸を押さえ……逃げるように踵を返して陣幕へ戻る。
何かが気になったが、それだけだ。
あと数日、数週間、数か月後に戦いが始まる。
腹を空かし、戦う気力を無くし、それでも金のために戦う愚者――それらを一方的に虐殺する戦いが。
それに、その『何か』は必要ないと、リリスは捨てた。
<<前の章
|
次の章>>