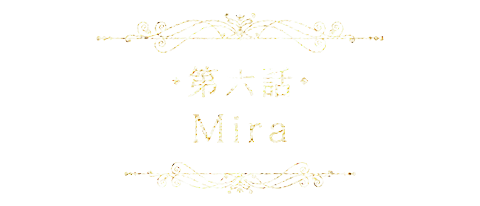
その部屋には、甘い花の香りが漂っていた。
窓から見える建物の周囲に民家は見えず、周辺は緑――草原や森に囲まれ、近くには川が流れている。
空には昼間だというのにうっすらと星が浮かび、太陽よりずっと近い位置に七つの惑星が存在していた。
色とりどりの、それこそ巨大な宝石が空に存在するかのような光景は幻想的で、そんな空を大小さまざまな鳥が飛び、草原を獣が駆けている。
風が木々を揺らす音。
川のせせらぎ。
小鳥のさえずり。
獣の遠吠え。
正しく『自然』な光景は見る者の気持ちに安らぎを与え、清浄な空気は落ち着きを抱かせる。
そんな世界の果てにひっそりと建つ建物……学校。その中にある教壇に立つ女性が歩くと、ギイ、と木造の床が僅かに軋んだ。
動きに合わせて濡れ羽色の髪が揺れ、窓から差し込む陽光に照らされてその色を濃くする。
その輝きはまるで黒曜石のよう。しかし、絹のごとき滑らかさで肩から滑り落ちる。
身に纏うのは髪と同じ黒色のワンピースドレス。
レースとフリルで飾られたドレスと漆黒とも言える髪とは対照的に、その肌は真っ白。黒衣を纏っているからか、余計にその白さが際立つ印象だ。
女性が、教壇の一段高い場所から男女合わせて十五人の生徒を見下ろしている。
時間にして数分。
生徒たちは動かない。
全員が目を閉じて集中している様子は、誰もが知る学校の授業という風体ではない。
けれど、生徒たちは文句を言わずに集中――ギイ、ギイ、と。床がきしむ音だけが教室に響く。
ギイ、ギイ。
軋む、軋む。
床が軋む。小さな音が十五人の耳に入り込んでいく。
ゆっくりと、ささやくように。
耳から頭に、そして体の中に。
女性が歩く。
その気配が動く。
教壇から降り、生徒たちの傍へ――。
「エヴェン、集中できていますか?」
十五人の中で最初に集中力が切れたのは、そんな女性と同じ黒髪の男子だった。
名前を呼ばれて顔を上げると、大きく息を吐き――ゆっくりと吐く。
「大丈夫よ。落ち着いて……ゆっくり息を吸って、吐いて」
黒髪の女性――リリスはエヴェンと呼んだ男子が座る席の後ろへ回ると、その肩に手を置いた。
お手本のように深呼吸を行い、それに倣ってエヴェンと呼ばれた男子生徒も深呼吸を数回繰り返す。
気持ちが落ち着いて、また目を閉じる。
以前の――カイオス王国の内乱で殺意を振りまいていた彼女とは違う、やさしい声音。
彼女を知っている者が聞けば、まるで別人のような声。
そう、この場で同じように目を閉じて集中しているリースとミラは感じる。
目を閉じているからこそ感じる、リリスの変化。
それが、ゆっくりと歩く彼女の足音と一緒に、耳から入り込んでくる。
重なっていく。
合わさっていく。
リリスと十五人が繋がり、重なり、一つになって、一人になって――また十六の意思に分かれる。
それは、不思議な光景だった。
太陽が高い位置にある時間帯。
だというのに、その教室の中は蒼く、薄暗く、そして寒々しい。
冷気――ではない。
その教室、この空間だけが歪む。
時間の流れから外れ、太陽の光すら水面で遮られたかのように揺らぎ、それが徐々に濃くなっていく。
「――そこまで」
リリスがパン、と手の平を叩き合わせた。
ただそれだけで、歪んだ光景は一瞬で正常の景色を取り戻した。
「目を覚ましなさい」
その言葉が耳に届くと、十五人は一斉に目を開けた。
全員の額に汗が浮かび、息が乱れる。
心臓が壊れたように早鐘を打っているのに、体の芯は氷のように冷たい。
その冷たさは、リリスから流れ込んだものだ。
教室を覆っていた蒼――それが十五人の中に残っている。
何度、繰り返しただろう。
そのたびに、十五人の中にリリスの魔力が流れ込み、蓄積していった。
けれどまだ足りない。
リリスはその思いを、ゆっくりと呼吸と一緒に飲み込んだ。
「お疲れ様。今日はここまでにしましょう……リース、話がありますから学長室に」
「わかりました、リリス先生」
燃え盛る炎を連想させる赤い髪は以前のままに、この二年で蕾のような少女から、ただ一凛だけ咲く孤独なバラを思い起こさせる美しい女性に成長したリースは、難色を示すことなく返事をした。
周囲の生徒達の視線が、一瞬だけリースに向く。
この学校が開設されて二年という時間が流れている。
ここは魔女の学校。魔法の学び舎。
カイオスの内乱が落ち着いた後、王城を出たリリスが魔法を学ぶために建て、そして今は魔法の才能を持った子供たちを集めて開いている学校。
ここに居る全員が家庭に問題を持ち、中には両親と死別した者も。
そんな生徒たちにとって人並み以上の知識を学ぶ場を提供してくれたリリスは恩人であり母親のような存在であった。
けれど、そんなリリスが何か頼み事をするのは、この中で最も長い付き合いのリースであり、それを羨ましいと思いながら見つめる視線。
嫉妬、ではない。
年代がばらばらの生徒達にとって、リースもまた姉であり妹のような存在だったから。
ただただ、彼、彼女らは羨ましいとリースを見る。
いつか自分たちもリリスに頼られたい――そう思われるほど、リリスは生徒達から慕われていた。
そんな視線に気付きながら反応を示さないリースを見ながら、リースと付き合いの長いミラはため息を吐く。
リースがそうであるように、ミラもまた、この二年で美しい女性へと成長していた。
肩まで伸びたクリーム色の髪と常に浮かんでいる柔和な笑みは男子生徒達から人気で、赤髪のリースがバラなら、白い衣装を好むミラは白百合に讃えられていた。
リリスの魔力を感じるという授業が終わって僅かにざわめく教室内で、ただミラだけがリースを心配し……そして、表情を暗くしていた。
けれどそれは微々たる変化で、ほとんどの生徒達は気付かない。
「それでは、後は自由時間に。明日は先日教えた魔法の実践を行いますので、授業の復習をしておくように」
そう言って、リリスはざわめきが残る教室を後にした。
十代半ばから二十代前半の子供たちが集まる教室だ、賑やかなのは良いことだと思いながら、生徒達から見えない位置まで移動すると口元が僅かに緩んでいた。
その雰囲気は柔らかく、温かい。
厳しさの感じられないリリスは年相応の落ち着きを手に入れ、その美貌はリースやミラとはまた違った人気で生徒達を魅了する。
「大丈夫か、ミラ?
顔色が悪いぞ。」
そんなリリスを目で追って、見えなくなってからミラがため息を吐くと、一人の男子が声をかけてきた。
授業中、注意を受けた黒髪の男子、エヴェンだ。
170センチを超える長身を持つ男子だが、今はミラの確認するために腰を曲げている。
突然近くに男子の顔が現れて、ミラは声には出さなかったが少し驚いた。
「体調が悪いのですか、ミラさん?」
そんなエヴェンの声を聴いて心配そうに歩み寄ってきたのは、そんなエヴェンよりもさらに高い身長を持つ、栗色の長髪をゴムで一纏めにして肩から流す美貌の男子、キンダー。
身長のせいか、エヴェンと同い年の彼は、この教室で一番の年上に見える。
「いきなり声をかけて顔を寄せて――女子を驚かせてどうするの」
そんな男子二人を冷めた目で見るのは、この中で一番年上である紫髪の女性、ジェシカ。
彼女もミラを心配して傍に来たが、ミラは深呼吸をしていつもの調子を取り戻した。
落ち着いた雰囲気を纏い、表情を柔らかく緩ませ、何でもないと微笑みを返す。
「少し、魔法の授業で体調が悪くなっただけです」
「お部屋で休んだら?
夕食時に起こすけど?」
「そうですね――そうさせてもらいます」
二年という時間、この学校で共同生活をしている友人に嘘を吐くのは心苦しかったが、ミラはそう言って教室を後にする。
気分が悪いのではない。
こればかりはどうしようもないのだと、自分でも思う。
言葉通り、気分の問題だ。
カイオスの内乱で孤児になり、リリスに拾われた。
感謝している。
彼女の養子となったおかげで、ミラはたくさんの友人を得る事が出来た。普通に生きていたので映える事が出来なかったはずの、魔法という英知に触れる事が出来た。
本当に、心から感謝している。
けれど同時に、カイオスの内乱を起こして両親を失う原因を作ったリリスを……憎んでもいる。
深く暗い感情は、小さいけれどミラの心の中に確かなものとして存在してしまっていた。
でも、と。
ミラはリリスが戦いを起こした理由も知っていた。
最愛の兄を奪われ、国を私物化した父に愛想を尽かし――父王を殺し、その父王と結託していた貴族を討った。
その本心は国を想っての行動ではなかったとリリス本人の口から聞いていたが、その行動は彼女の兄が愛したカイオス王国を救うきっかけになっていた。
だから、ミラは二年という時間を経て、リリスを慕い、同時に、消える事のない憎しみが胸を苦しめる
それが、ここ最近は顕著であった。
校舎の離れにある宿舎まで戻ると、生徒一人一人に割り振られた個室――間違えることなく自室へ戻ると、ミラはそのままベッドに腰を下ろした。
好きか嫌いかで言えば、リリスのことは好きだった。
だから迷う。
困ってしまう。
どうしたらいいのだろう、と。
こんなことを相談できる相手が、ミラには居なかった。
ミラ以上にリリスを慕うリース、学校の友人たち。
相談したらそれら全部を失ってしまいそうな不安を感じ――ミラは悶々とした気持ちのまま、ため息を吐く。
「……そうだ」
気持ちを切り替えよう。
ミラはそう思うと、ベッドの上に居住まいを正した。
胸を張り、背筋を伸ばし、顎を引いて前を見る。
目を閉じると、体の奥、その芯――ミラという形の中にしっかりと存在しているリリスの魔力を感じる事が出来た。
ミラはこの時間が一番好きだった。
リリスから魔力を与えられるのではなく、リリスの魔力を感じる時が。
カイオス王国でリリスと再会した時を思い出す。
あの時、何かを感じたような気がした。
今思うと、あれがリリスの魔力だったのだとミラは思う。
集中。
不幸なのは――ミラに魔法の才能があったことか。
それとも、ただただ運が悪かっただけなのか。
「え?」
気が付くと、目の前に扉があった。
蒼色の扉――それは、ミラの内にある魔力が具現した、異界へ通じる扉。
一瞬だった。
けれど深く、鮮明に思考した――リリスとの思い出の場所。
養子として受け入れられた場所。
カイオス王国へ通じる扉。
それが、目の前に在った。
<<前の章
|
次の章>>