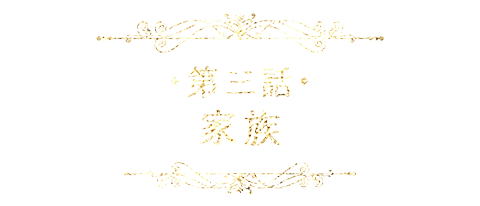
「なるほど。とても不思議な話だね、リリス」
部屋の中に、朗らかで高い、元気な声が響いた。
それはもちろん黒髪の美女――リリスではなく、先日、老人から半ば無理やりに託された赤い髪の少女リースでもない。
リリスの兄であり、カイオス王国の第一王子シヤウン。その人である。
リリスと同じ艶のある黒髪は動きやすいように短く切られ、肌は外によく出ているからか健康的に焼けている。
戦場に出て鍛えられた筋肉質な腕はリリスよりも二回りは太く、その大きな手がこの部屋で一緒に暮らしている赤髪の少女の頭を優しく撫でていた。
「それで、君の名前は?」
「リースです、シヤウン王子」
リースと名乗る少女は、特別な警戒をされることなく城の中で生活していた。
突然現れた奇妙な少女――とリリスは思うのだが、だからといって不気味と思うわけでもない。
警戒心は消えていないが、敵意を抱くほどでもない。
不思議な感覚は、先日――突然現れて突然消えた老人に感じたものと似た感覚。
同時に、あの時に見た夢の内容と、自分自身に抱いた違和感を思い起こしてしまうのだ。
自分が体験したことのない、けれど確かに知っている……ソレが、自分自身に馴染んで、混ざり合っていく……奇妙な感覚。
自分が自分ではない他人になっていくような違和感は、昨日まで確かにリリスを怯えさせていた。
けれどそれも、今はない。
兄が……この国で唯一信頼できるシヤウンが、リリスをリリスと認識してくれたからだ。
「不審人物が入り込めるほど穴だらけの警備でもないはずだが……信頼できる兵を増やしておこうか」
「ありがとうございます、お兄様」
シヤウンはリースを撫でながらそう言った。
そのリースもその不審者と一緒に来たのだが、こちらには特別な警戒をしている様子はない。
少女という外見もあるだろうが、リースに敵意がないのを理解しているのだ。
実際に、リースにはリリスを害するという意思はなく、ただただモンと名乗った老人がリリスに面倒を見てもらうようにと言われたからここにいるだけ。
今はまだ、それだけだった。
あとはまあ、老人との旅では味わえなかった焼き菓子や砂糖菓子――人生で初めて口にした甘いものの味がとてもお気に召した、というのもある。
不思議と、彼女を傍に置くことにリリスは抵抗がなかった。
むしろ、城の貴族達よりも……あの得体のしれない老人の方が信頼できるとすら感じている。
理由はない。
勘。もしくは本能、とでもいうべきなのか。
だからリリスは、リースという少女を傍に置いた。
父王に一応の報告をしたが――彼はどうやって上手く戦争を操るかに執心して、気にしていない様子であったのを、少しだけ悲しく思う。
父の興味が自分にない。
それが、リリスは少しだけ、ほんの少しだけ悲しかった。
「ふむ……俺には普通の人間にしか見えないな」
「そうですね」
リースが無感情ながら、丁寧な言葉を返す。
その中にあるほんの僅かな感情の機微を察して、シヤウンはリースに敵意がないと感じていた。
自分に向けられる感情を敏感に察する能力に関してなら、シヤウンはリリスよりも数段優れていた。
それは子供のころからだ。
そんなシヤウンも悪意を感じないなら、リースに悪意がないのだろうとリリスは改めて思う。
そして同時に……戦場から戻ってきたシヤウンを見て、リリスはため息を吐く。
王子というにはその肉体、その意志は、あまりにも『戦場』に向いている……兄が戦争から戻ってくるたびに、リリスはそう思う。
戦うたびに、剣を握るたびに、人を斬るたびに――兄がこの王城から、自分から遠ざかっていくようだ、と。
そのリリスの兄は座り慣れた木造椅子に体重を預けながら、先日この城の新しい住人となった赤髪の少女の方を見た。
少女もまた、相手がこの国の第一王子だと分かったうえで、気負いなくその瞳を見返す。
妹と同じ青色の瞳と、髪と同じ赤い瞳が交わったのは、数舜。
「君はリリスに似ているな」
「そうですか?」
「ああ。必要なこと以外は口にしないで様子を伺っているところはそっくりだ」
「……お兄様、それだと私がとても無口で不愛想な人間のように聞こえるのですが?」
シヤウンの言葉にリリスが呆れながら抗議の声を上げた。
心外だと言外に告げるとシヤウンが笑い、その笑みを眺めていたリースもわずかに口元を緩める。
初めて見た赤髪の少女の笑みに、ほう、とシヤウンが驚きの声を上げた。
「昔のリリスもこんな風に笑っていてくれたのだが」
「お兄様?」
リリスの声音が一段低くなる。
怒った口調だが、芯からの怒りは感じない。
懐かしい兄弟のやり取りだ……だからシヤウンも謝罪の言葉は口にせず、気づかないふりをしてリースの髪をまた撫でた。
昔、妹にしていたのと同じように。
「どうした、リリス。眉間にしわが出来ているぞ」
「いえ……お兄様こそ、戦場に出てお疲れでしょう?
お部屋へお戻りになられては?」
「おや、珍しい。お前が俺を心配してくれるなんて」
「いつも心配しているつもりですが」
尖った口調は続いており、シヤウンが苦笑する。
からかいすぎたか、と内心で反省した。
……老人と少女が突然部屋に現れた。それこそ、煙のよう。
そんな話など、だれが信じられるか。リリスもこの事は今日、戦場から戻ったばかりの兄に伝えるまで誰にも言えなかった。
言えば気が狂ったと思われ、貴族連中に弱みを握られると理解していたからだ。
兄が立つ場所が剣と弓の戦場なら、リリスが立つのは弁と策略の戦場だ。
弱みを見せれば付け入られ、養生という名目で王城から遠く離れた別荘へ送られかねない。
そうなれば貴族連中が言う『金儲け』の話に耳を傾ける王を咎める人間が居なくなる……最近は娘の言葉にすら煩わしさを感じている節すらあるのだ
いまリリスが王城から離れれば、王は民の犠牲など一顧だにしない悪政を敷く可能性があった。
「それでは俺は、そろそろお暇するよ――お前をこれ以上怒らせると後が怖いし、父上に報告することもあるしね」
「はい。もしまた無理難題を押し付けられましたら、遠慮なく私を頼ってくださいね」
茶化すようなシヤウンの言葉。けれど返事の声音が固くなるのをリリスは自覚した。
リリスが年相応の笑顔を浮かべなくなったのは、母親が死に、父王が民に重税を強いるようになってからだ。
シヤウンはそのことを思い、内心でため息をつく。
本当ならば戦争など止めて、国を豊かにするべきなのだ。
富国こそが王の使命であり、民の拠り所である。戦争を続けて民を苦しめれば、民心は王から離れ、国が成り立たなくなる。
そんなこと、誰でも分かっているはずなのに――そんな当たり前を行う目すら曇らせてしまうものなのか。
富という名の甘美な毒は。
「確か、突然現れた老人はモンと名乗ったのだったか。その老人については俺の方でも調べておこう。部下に噂話が好きな連中が数人いる」
「お願いします、お兄様」
リリスは自分でも意図せず、低い声を出し、若干鋭くなった目でシヤウンを見た。
並みの人間ならそれだけで言葉に詰まり背に冷や汗を流すだろう視線だったが、シヤウンは気にした様子もなく、口元の笑みも緩めない。
「お兄様もお気をつけて」
「ああ、大丈夫さ。ちゃんと、また無事に帰ってくる」
それもまた、リリスとシヤウンの悩みの種であった。
当然だ。
いくら武芸に心得があるとはいえ、最前線に自国の王子を出すなど正気とは思えない。
それで兵士の士気を高めることができるとはいえ、もう長年続いている隣国との戦争だ。今更局所的に勝利しても、意味などほとんどない。
勝敗は戦の常。
大勝を続けてこそ意味があり、今のように勝ち負けを繰り返している状況では国の跡継ぎを失うという最悪を招きかねない悪手。
……そう考えているうちに、シヤウンはリリスの部屋を後にした。
あれほど騒がしかった部屋が、一瞬で静寂に包まれる。
それだけリリスとリースは無口であり、シヤウンは饒舌に喋っていたということの証明だった。
「大切な方なのですか?」
しばらくして口を開いたのはリースだ。
それは、少女が謎の老人に連れられてきてから初めて、自分から口を開いた瞬間でもあった。
「当然でしょう。家族、なのだから」
「家族」
リースは数度、その単語を口の中で繰り返した。
まるで何度も咀嚼するように、意味を食みながら自分の中に取り込んでいく。
「リリス様、ロンが言っていたことを覚えていますか?」
「……政治にかかわるな、だったかしら?」
「いいえ。歴史に干渉するな、です」
リリスの間違いを正し、リースはシヤウンが出て行ったドアの方へ視線を向ける。
当然だが、もうそこにシヤウンの姿はない。
その日の夜、シヤウンはリリスにも告げず、護衛の兵士を伴って前線へと戻っていった。
リリスがそのことに気付くのは翌日で、そしてそれは遅過ぎた。
カイオス王国と隣国・オルダー公国の戦争はさらに激しさを増していく。
まるで、シヤウン王子が戦場へ戻ってくるのを待っていたかのように……。
リリスは気づくべきだった。
いや、弁は達者でも戦場を知らない彼女に気付けというほうが無理だったのか。
戦場に立つ自国の兵士も、所詮は人間なのだ。
多額の金銭をちらつかせれば、家族の無事を担保にすれば、昇進の契約が結ばれれば、簡単に裏切る。
その対象が、自国の王子であっても。
戦争は激化する。
けれど、戦争が終わることはない。
両国ともに、戦争は『金のなる木』なのだ。
そして、心から戦争を終わらせようと願っている者こそ、邪魔であり、真の敵でしかない。
リリスは、その事に気付くべきだった。
けれど、気付けなかった。
だから、彼女は失った。
家族を。
数日後、カイオス王国第一王子シヤウンの死が伝えられ、戦争はさらに混迷を極める。
そして、リリスは知る。
シヤウンを裏切った兵士、彼らを操っていたのが父親である事に。
<<前の章
|
次の章>>