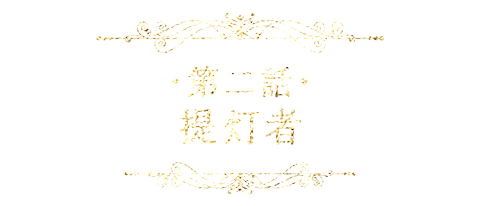
――その目覚めは、最悪だった。
「……ここは?」
どこだっただろうか。
言葉と思考で自問し、黒髪の女性は眠っていた柔らかいベッドから上半身を起こした。
体が強張っているのを自覚する。
腕を持ち上げるだけで肘と肩に鈍い痛みを感じ、顔を顰めた。
次に感じたのは寒さだ。
周囲を見回すと、石造りの壁。豪華ではないが白い石壁によく映える調度品の数々。壁に立てかけられた動物の頭部のはく製が視界に映った。
見覚えがある。
ここは、自分の部屋だったはずだ。
「ええ、そうね」
そう、自分に言い聞かせる。
ここは自分の部屋で、そしてさっきまでの光景は夢……のはずだ。
けれど夢は現実だったかのように緑の匂い、涼やかな風、少年の感触――そして、水の冷たさを身体が覚えている。
右手で、左の二の腕を掴む。
まるで氷のように冷たくて、本当に『湖でおぼれた』ようだった。
「ふう」
気持ちを落ち着けるために、深く息を吐く。
まずは現状をちゃんと認識するために目を閉じ、思考の海に意識を沈めていく。
ここはエスタリアの大地の一角を支配するカイオス王国、その首都にある王城の自室。
カイオス王国は隣国であるオルダー公国との戦時下にあり、その戦いは日増しに激しくなっていた。
彼女の兄であり王国の第一王子であるシヤウンは連日の用に戦場へ出ては武功を立て、その勇猛さをこのエスタリアの大地に知らしめ、味方からは称賛を、敵国からは畏怖の念を集めていた。
一本の剣を手に戦場を駆ける勇敢さとは裏腹に、民には優しく自国とはいえ貴族の不正に嫌悪を示す清廉潔白さで民から愛される兄。
そんな兄とは対照的に、その妹は常に物憂げな表情を浮かべている人物だ。
黒曜石を溶かしたような濡れ羽色の髪を持つ女性の名前は、リリス。
カイオス王国第一王女にて、王国内の貴族達に掴まって政治という蜘蛛の糸に囚われた哀れな黒羽の蝶――ではなく、蜘蛛となって人の悪意を食む者。
黒い髪に病的なまでに白い肌。
白のフリルで飾られた青いワンピースドレスと、空色の瞳。
右の目元にあるほくろが印象的な、陰のある美女。
陰鬱で妖艶、さりとて弁の立つ彼女は貴族や一部の国民たちからはあまりよく思われていない。
そもそも、女が政治に口を出す――というのがこの国では法度なのだ。
自分の置かれている立場を『思い出して』から、彼女はその美しい黒髪を掻き上げて端正な顔に口元だけを歪める独特の笑みを浮かべた。
視線を窓の方へと向ける。
白いレースのカーテンに遮られていても分かるのは、今が夜だという事。
そして、どうして自分がこの時間まで眠っていたのかという疑問が新しく浮かぶ。
記憶はちゃんとしている。
自分はリリスだと言える。
けれど、自分の中に別の何かが居るような、今日までの記憶にはなかった新しい別人の記憶が入り込んだような、違和感。
白い絵の具の中に赤いペンキが落ちたような異物感。
自分はリリスなのに、別の何かに変わってしまった……それは、時間を置くほどに『馴染んでいく』のが分かった。
けれど、それも、どうでもいい事。
それはとても大切なことのはずなのに、それほど重要とは思えない。
本当にただ『どうでもいい』と感じながら、リリスの思考は既に別の方へ向いてしまっている。
リリスは手を伸ばしてカーテンを引くと、窓から見えるのはカイオス王国の街並み。
宙にある月と星、その中でも強く輝く『六つの星』が照らす、カイオスの夜景。
建物の窓から漏れる火による暖色の明かりは人の営みを表し、その数は無数。
うっすらと暗闇の中に蒼く浮かぶのは石造りの建物と、白石によって舗装された道。
地面が露出している場所は僅かで、そのほとんどが石材、ないしは木材で補強されている。
月明かりの下に浮かぶ王都の街並みはいつも以上に鮮明で、それは頭上にある真っ白い月が真円を描いているからだった。
そんな暗闇の中に浮かぶ王都に残っているのは女子供ばかりで、男性の多くは戦争に駆り出されている。
戦争。
無意味に争い、無意味に命が消え、戦火は人の営みだけでなく大地を疲弊させ、百害あって一利すらない自己満足。
どれだけ戦争の無価値を説いても戦争を必要だと貴族達は民を煽り、扇動する。
金になるからだ。
戦争が続けば武器が売れる。薬が売れる。食料の価値が上がる。
勝てば土地が増え、奴隷という名の労働力を得ることができる。
負ければ土地と労働力が減り、稼ぎが少なくなる。
金が動く遊戯……それが貴族たちの戦争だ。
民には一銭も回らず、貴族の懐が膨らむ。
貴族の悪意が憂国の善意に隠れ、それが悪徳の腐敗を増長させる。
だから貴族は戦争を望む。
戦火が届かない、戦場から最も遠い王城の中で。
考えながら、リリスは兄と約束していたのを思い出した。
戦争を止めると。
兄が武勇に優れているなら、妹は弁論に優れていた。
ただそれは言い訳で、シヤウンがリリスを戦場に出したくなかっただけなのだろう。
リリスはそれに気付いていたが、それでも約束をした。
戦争を煽る貴族を、その口車に乗ってしまった国王である父を、説得すると。
そのことを思い出して、リリスは血がにじむほど唇を噛んだ。
「ふむ、無事に目を覚ましたか」
「――――え?」
その声は突然耳に届いた。
慌てながら声がした方へリリスが視線を向けると、時折、部屋を訪ねてきた兄がよく座っていたしっかりとした造りの木造椅子、そこに一人の男性が座ってキセルを咥えていた。
火は付いていない。
ただ咥えているだけなのが印象的な――老人だ。
胸まで伸びる長い灰色の髭と、おなじく草臥れた灰色の……ぼろ衣と見紛うようなローブ。
そして頭には、まるで御伽噺で語られるような大きな三角帽子。
ギイ、と。
老人が困惑するリリスをからかうように椅子へ体重を預けて軋ませた。
「気分はどうかな、リリス」
自分の名前を呼ばれたことに驚き、リリスが警戒を強める。
それを視線で感じた老人は、わざとらしく咥えていたキセルを懐にしまい、居住まいを正した。
「それとも、別の名前で呼んだ方がいいかね?」
「……別?」
老人が何を言いたいのか分からず、リリスはベッドから足を下ろしながら老人に向き直った。
丁寧に手入れをしている黒髪が、肩から胸元へと落ちる。
まるで黒い滝だ、と老人は感心した。
「噂には聞いていたが、うむ。噂にたがわぬ美しさよな」
「……衛兵を呼んだ方がいいですか、ご老人?」
「冗談じゃ。褒めただけではないか」
老人は右手を上げ……そこでキセルを持っていないことに気付いたようだった。
キセルを咥えるのが癖なのだろう。
リリスはそう考えながら、溜息を一つ。
不審な老人だ。
夜更けに自分の部屋――しかもただの民家ではなくここはカイオス王国の王城。その中でも警備が険しい第一王女の私室……だというのに、まるで風のように侵入してきていた。
警戒するなという方が無理なのに、けれど王城内にはびこる悪意――貴族達が向けてくる害意のようなものは感じない。
衛兵という単語もつい口から出ただけで、今のリリスには呼ぼうとする意思はなかった。
それを悟ってか、老人も気にした様子はなく椅子に体重を預けてギイ、と鳴らした。
「今日は忠告に来ただけじゃ」
「忠告?」
「リリス。お前は今日から、歴史に干渉するな。政治にも、戦争にもだ」
「…………」
「王族であるお前には発言力があり、その行動には良くも悪くも結果がついて回る……今日からのお前は、なおさらじゃ」
リリスがその端正な表情から感情を消して睨みつけると、老人は黙ってしまう。
リリスの視線には、それだけの凄味があった。
口と意思を黙らせるだけでなく、まるで魂すら射抜きそうな鋭い視線。
だから黙り……それに、老人が訪れた本当の理由はそんな事を伝える為ではなかった。
「まあよいか。今のお前なら、どうすべきかすぐに気付くじゃろ」
「……意味の分からないことを」
「性分じゃ。何百年と生きると、性格というのはもう変えられん……それより」
いつの間にか、今度はその手にキセルではなく古ぼけたランタンが握られていた。
漏れる明かりは、橙の暖色。
何の変哲もない――けれど明かりのある室内で使うには違和感を覚える。
老人がそのランタンを軽く揺らした。
リリスの視界の中で、暖色の明かりが尾を引いて動く――。
――気が付いた時には、老人のすぐ傍に『真っ赤な少女』が立っていた。
年のころは十四、十五歳程度。
老人と同じ質素な衣服を纏っているが、その髪は燃え盛る炎のような深紅。
その目付きは鋭く、しかし雰囲気は物静か。
ただその真っ赤な髪が、突然現れた鋭い目つきをした少女の内心を表しているようだった。
だがリリスは、突然現れた少女を見ても驚いていなかった。
むしろ、ああ、なるほど。この老人はこうやって現れたのかと納得すらしていた。
理屈ではなく本能――なぜかそこに、疑問は浮かばない。
「名はリース。お前が育てよ、リリス」
「……なぜ私が貴方の命令を聞かなければならないのですか?」
「命令ではない。これはお前の為だ」
それだけを言って、リリスの怪訝とも呆れとも取れる視線を気にすることなく老人は椅子から立ち上がった。
赤い少女がぼんやりと老人の動きを目で追い、老人はただ軽くその頭を撫でるだけ。
視線すら向けていない。
「ではな、リース。もう会う事もないかもしれんし、また会えるかもしれん。願わくば長く生き、達者に暮らせよ」
「はい。ではまた、モン」
「うむ――リリス。お前はくれぐれも、歴史には干渉するなよ」
老人は再度そう告げると、リリスの返事を待たずにまたランタンを軽く揺らし……その姿が部屋から消えた。
リリスがドアの方を見るが、開かれた様子はない。
夢でも見ていたような非現実的な時間だったように思う。
けれど、リリスの部屋には真っ赤な少女――リースが老人と別れた時のまま、座る者が居なくなった椅子の隣に立ち尽くしていた。
<<前の章
|
次の章>>