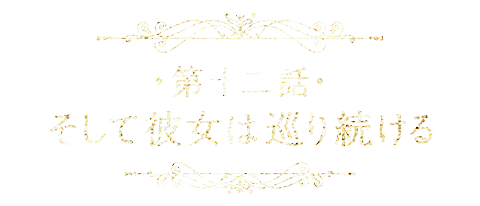
それは、思っていた以上に『悲しい』と感じた。
人からはよく無表情、無感情と言われても、自分が感じている思いが人並みとはとても言えないのだと分かっていても、それでも……自分にも感情はあるのだと思っていた。
だから――リリスの死を感じ、モンの焦る姿を見て、この場に辿り着いた時――リースは自分の心が乱れるのを、しっかりと感じていた。
「リリス先生」
欠片エリアに横たわる亡骸を見た時、その感情が『悲しい』というのだと、理解した。
その体を抱き上げる。
冷たかった。
この肉体にはもう魂が宿っていないと確信させる冷たさは、抱き留めたリースの体から熱を奪うように冷え切っていて……それがまた、リースを酷く悲しませた。
涙は、出ない。
そういえば、と……リースは思い出す。
リリスは、兄であるシヤウンが死んだときも涙を流さなかった。
悲しかったはずなのに……と。
この時になってようやく、その時のリリスの気持ちが少し分かったような気がする。
「お疲れ様でした――リリス先生」
カイオス王国のために命を懸けたシヤウン。
最後まで生徒のことを考えていたリリス。
リリスが今際の際に想った「生きて」という願いはリースに届き、だからこそ、その言葉がリースの悲しみを少しだけ癒してくれた。
死の直前まで他者のことを考えていた兄妹なのだから、悲しむよりも、嘆くよりも、お疲れ様という労いの言葉を送りたいとリースは感じた。
「あ」
ふと、視界の端に映ったのは美しい宝石――蒼色のベリル……アクアマリン。
リリスの魔力と同じ色をした深い蒼の宝石がリリスの亡骸から零れ落ちた。
抱きしめたリリスの遺体を離さないように片手で強く抱き、もう片方の手を宝石に伸ばす。
指先が宝石に触れると、そこにリリスの魔力が宿っているのが分かった。
いや、違う。
これはリリスの魔力が凝固し、練り上げられた魂魄石――。
「……どうして?」
どうして自分はこの石の名前を知っているのだろう。
リースは不思議に思いながら、その石を手放さないようにしっかり握り、リリスの遺体と一緒に抱きしめた。
「リリス先生。帰ろう、学校に――」
せめて、遺体は彼女の人生の中で最も幸せな記憶が詰まった学校に。
脱力したリリスの遺体は、不思議なほど軽かった。
それはまるで、リリスが早く学校に帰りたいと思っているかのようで……また、リースは悲しくなる。
「すぐにつきますから――そうしたら、体を清めて、ベッドで眠りましょう。ここは――寒過ぎます」
枯れた木々に囲まれた場所。
ここは景色もよくないし、気持ちが冷たくなる。
リースは無意識にリリスの遺体へ、彼女が寂しくないように語りかけながら、息を乱して歩いた。
不思議だった。
移動しながら、リリスの記憶が、感情が、リースの中に流れ込んでくる。
いや、蘇ってくると表現した方が正しいだろう。
涙が出るほど悲しくて、声が漏れるほど嬉しくて……それはリースが知らないはずの記憶。
なのに、鮮明に思い出せるリリスの記憶。
魂魄石は持ち主の記憶を残し、資質がある者に譲渡する記録の石。
リリスは魔女の本能でその記憶を、意思を、魔力を、魂魄石として残し――リースには彼女の全部を受け取る資質があった。
それを偶然という一言で片づけるには無理があり、きっと最初からモンはこのことを知っていてリリスとリースを近づけたのだと、悟る。
それを悪いとは思わない。
怒りも沸かない。
ただ――リリスの記憶が自分の中に残る。
そこに少しだけ救いがあるように感じて、リースは悲しみ一色だった胸に暖かな色が零れ落ちるのを感じた。
「ああ、本当に――私たちが居た時間は長かったようで、すごく短かったのですね」
リリスの記憶。『蒼の魔女』の記憶。
王族として産まれ、父親である王の愛は自分でも国でもなく金に向き、兄だけが心の支えだったのに失い、憎しみに狂い、それでも正気を失えず――戦場を去った。
リリスは善人過ぎたと、記憶を覗きながらリースは思う。
兄の為に狂い、内乱で苦しんだ人たちを見て正気を取り戻し、自分が人生を狂わせた人たちを救いたいと懊悩し続けた数年間。
最後は魔女を恐れた前カイオス王側近の大臣との争いに巻き込まれたミラを想い、自分が生きている限り生徒たちが不要な争いに巻き込まれる……その未来を断つために命を絶った。
それが、最初の魔女。蒼の魔女の最期。
自分以外の者の為に狂い、自分以外の者の悲しみで正気に戻り、自分以外の者を想いながら死ぬ。
……その人生にリリス自身を想う人はおらず――この魔女はずっと独りだったのか、と。
ただ、最後の数年間。
学校での暮らし。
教師として、母として、生徒を、リース達を愛したリリス。
そんなリリスを慕い、母のように想い愛したリース達。
その数年間だけは、幸せで、穏やかで――毎日が楽しかったのだ。
本当に、心から……リリスは十五人の生徒を愛していた。
リースはそんなリリスの亡骸を強く抱きしめ、体温が残らないその胸に顔を埋めた。
「ゆっくり休んでください。もう、」
貴女を苦しめるものは何もない――そう口にしようとして、留まった。
記憶が続く。
遡る。
リリス自身ですら自覚していない、けれど漠然と心に残っていた記憶。
いや、記憶とも言えない――なにか。
リリスの記憶を魂魄石から受け取れるリースだからこそ理解できる、もう一つの人生。
それは、リリスが魔女としての力を手に入れる前。
モンが干渉する直前。
リリスとリースが出会った日。
第三エスタリアの住人であるはずのリリスに、違う世界の記憶が混じっていた。
いや、リリスに何者かの魂が混じったのか。
どこかは、分からない。
ただ、ただ――そこが魔女の始まりなのだと、リースの魂が理解した。
戦渦に追われた少女が最愛の少年を失い、そして絶望に身を焼きながら湖に身を投げた。
その冷たさを。
その悲しさを。
その悔しさを。
……そして、その歴史の修正を。
怨嗟の記憶。
改変の願望。
その思いは呪いとなり、その呪いは力となって……魔女を作り出した。
「ああ、リリス……リリス先生。貴女の旅はまだ終わっていない……いえ、始まったばかりなのですね」
学校が見えてくる。
リースの中に流れる記憶の奔流も、終わりが近づいてくる。
終わる。
終わってしまう。
……ただ、思う。
帰ろう。
一緒に、自分たちの家へ。
戦争は終わらない。
反乱軍の野望が潰えても、エスタリアの大地が統一されても。
それでも人間が存在する限り、その欲望は戦火となって人間を焼く。
それは、どのエスタリアでも同じ。
空に浮かぶ七つの惑星を見上げながら、燃え盛る炎を連想させる赤髪を肩まで伸ばした女性は、感情が読み取れない表情のまま、じっと立つ。
「リース先生。どうかしましたか?」
黒色の髪を持つ、まだあどけなさが残る表情の少年が名前を呼んだ。
声がした方へ振り替えると、腕白盛りの少年が明るい笑みを浮かべながら歩み寄ってくる。
まるで子犬のようだと、リースは口元だけを僅かに緩めて、歩み寄ってきた少年の頭を軽く撫でた。
少し、エヴェンに似てきたな、と。
「そうでしたね。ほかの皆さんは、教室に集まっていますか?」
「はい。今日もよろしくお願いします」
ここは、欠片エリアに存在する魔法の学校。
魔女が建てたこの場所には、魔女に連れられて才能豊かな少年少女が集う。
『蒼の魔女』の記憶と能力を受け継いだリースは、争いの螺旋から終ぞ降りることはなかった。
彼女は関わり続ける。
エヴェンが光の血族であることを否定しなかったように。
キンダーがその意志を曲げなかったように。
……ミラが、リリスの死を乗り越えたように。
他の生徒達が、その遺志を継いで世界を支えようとしているように。
リースは皆が帰る場所を守ることを選んだ。
この学校を。
皆の家を。
そして、『蒼の魔女』としての使命を貫き通す。
ジェシカだけは、彼女が今どこに居るのかが分からなかった。
ただ、彼女のことだ。
きっとどこかで頑張っているのだろう――そう思う。
「では、今日はどのようなことを教えましょうか」
「わかりやすくが良いな。先生の説明は言葉にしづらい感覚的な話ばかりだから」
「そうですね――魔女の力を言葉にできると簡単なのですが」
リースの生徒達は優秀だった。
言葉足らずなリースの説明をちゃんと理解して習得し、魔力の流れで彼女の意思を汲む。
教師としてまだまだ半人前のリースは、リリスもこうやって悩んだのかと思うと、少しだけ可笑しかった。
何でもできた最強の魔女、『蒼の魔女』リリス。
彼女もまた、毎日、生徒のことで頭を悩ませていたという記憶――それは、世界で一番幸せな悩み。
話しながら、視線を逸らした。
見たのは、欠片エリアの先。どこまでも続く、暗闇の果て。
まだそこをリリスの魂は彷徨っているのか。
それとも、魂魄石が見せた記憶の通り――彼女は頭上にある七つのエスタリア、そのいずれかに辿り着いたのか。
今はまだわからない。
けれど、それが分かる時は必ず来る。
そして、その時はそう遠くないという予感があった。
だから。
「リース先生、急ごうよ」
「ええ」
だから。
今は前を向こうと思う。
新しい光に寄り添いながら、歩いていこうと思う。
リリスの生徒。
皆の道がばらばらでも、いつか一つになってまた会える……そう信じて。
リースは今日も、魔女の家で教鞭を取る。
<<前の章
|