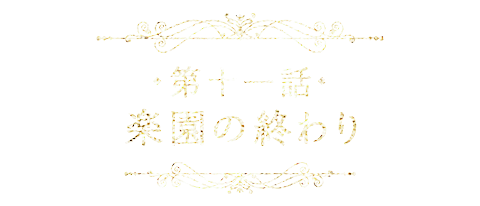
それからどうしたのかを、ミラは覚えていない。
気が付けば、彼女は第三エスタリアの世界に渡り――見慣れた、反乱軍の本拠地に立っていた。
古い砦を改築して使っている、ボロが目立つ石造りの建物だ。
簡素な木造の家具がいくつか置かれていて、天井付近には蜘蛛の巣がたくさん張っている。
とても衛生的ではなく、空気も汗臭さや放置された洗濯物や食器から上る異臭でよどんでいるようにミラは感じていた。
あの日。
リリスに隠れて魔法の練習をしてエスタリアスリップを成功させてしまったあの日に戻りたいと、ミラは何度も思った。
反乱軍の大臣に出会い、リリスのことを聞かれ……そして、同情された。
それが大臣の本心ではないと分かっていても、自分の中に在ったドロドロとした復讐心を聞いてもらうだけで、気持ちが軽くなるような気がしたのだ。
リリスが好きだった。大好きだった。尊敬していた。
けれど、実の母親を奪われたことを忘れる事が出来なかった。
その結果が、これだ。
リリスは、ミラの目の前から消えた。
彼女は自らその命を絶ち、もう手が届かない場所へ行ってしまった。
生気のない顔をしたミラを、しかし見ている人間はいない。
以前は数百人からなる反乱軍が身を潜めていた隠れ家の一つ――だがこの日は、誰もいなかった。
けれど、失意の底に居るミラはその事に気付かない。
「よく戻ったな、ミラ――」
「ぁ……」
その声は、反乱軍を率いるリリスの父親、カイオス王国の前王と懇意にしていた大臣と呼ばれている男の声。
ミラにリリスを殺すべきだと、殺さなければまたリリスが新たな争いを起こし、ミラのような子を生み出すことになると説いた男。
どうして、と。
どうして自分は、そんな言葉を信じたのだろう。
そんな言葉が頭から離れなかったのだろう。
ミラはリリスを信じていなかった自分に気付き、また泣きそうになった。
泣きそうになりながら顔を上げ――目の前に迫る白刃を、無気力ながら本能で避けた。
半身になりながら首を大きく逸らせると、首を狙った一撃が目の前を通り過ぎていく。
髪が数本、宙を舞った。
「ちっ」
「なに――?」
混乱。
体が動かない。
思考が固まる。
どうしてこんな状況なのか理解できないまま、ミラは剣を避けた体勢から動けず、男から蹴られて床を転がった。
木造の椅子や机を巻き込み、激しい音を立てながら石壁に背中を打ち付けた。
「ぁ、う……」
「本当に戻ってくるだなんて思っていなかったよ、魔女の生徒」
大臣は手に持った剣を油断なく構えながら倒れ伏すミラに近寄ってくる。
ミラは今でも現状を飲み込めず混乱し、大臣を見上げることしかできなかった。
何が起こっているのかわからない。
いや、どうして自分がここに居るのかも、よくわかっていなかった。
意識はいまだリリスと対峙したあの場所に置き去りで、ここに居るのは抜け殻なのだから。
「その様子だと、リリスを殺したのか? それとも失敗して、袂を分かったか?」
リリスを殺したという言葉に、ミラの肩が大きく震える。
殺した。死んだ。
――もう、この世にリリスは居ない。
そう考えると、瞳から涙が零れた。
殺したくなかった。
憎んでいたけど、それ以上に大好きになっていた。
だから――リリスがまた戦争を起こして、たくさんの人を悲しませるのが嫌だった。
欠片エリアでの平穏な暮らしが壊れるのが嫌だった。
だから、ミラは止めようとしたのだ。
……最初から、殺すつもりなんかなかった。
そのはずなのに、どこで歯車が狂ったのだろう。
いや、そもそも、欠片エリアへ戻った時から記憶に霞が掛かったように感じて、自分はどうしてここに戻ってきたのかもわからなくて――。
「なにを、私に何か――っ」
「なに。素直になるお薬だよ。少しばかり効きすぎて、自分の意志ではなく他人の言葉に素直になるお薬だったがね」
すでに、大臣はミラの正面に立っていた。
体が動かない。
思考に霞が掛かったままだ。
ミラは自分の置かれた状況を上手に理解できず、ただ何度でも思い出す。
欠片エリアに渡る前に飲んだ紅茶。
あれからだ。
あの時から体が不調を訴え、けれどそれを、リリスを止めるために緊張しているのだと思い込んでいた。
そして――そして、何度も、頭の中で声がした。
「それじゃあ、これで終わりだ。一緒に居ないということは、『蒼の魔女』は死んだか、貴様と袂を分かったのだろう? なら、お前など用無しだ」
大臣の声が。
リリスは戦争を起こす。ミラのように悲しむ人間を際限なく生み出すという言葉が。
何度も、何度も、何度も――。
「ああああっ!?」
石壁に背を預けるように座っていたミラの腹部に、剣が突き刺さる。
ミラは激痛に悲鳴を上げ、口から血を吐いた。
「その傷では、もう助からないさ。ここを知る人間は少ない――助けも来ない」
「はっ――はっ、はっ――」
息をすることも辛かった。
けれど、それ以上にミラの言葉で傷ついたリリスの心は痛かったのだと思うと、ミラは涙が出てくるのを抑えられなかった。
「ぅ、う……ごめん、なさい。ごめんなさい、リリスせんせぃ」
「ふん――さて、仕上げだ。『蒼の魔女』の支援を無くしたカイオス王国など、烏合の衆でしかない。邪魔が入る前にTabaiを落とさなければ」
ミラの腹部に剣を突き刺したまま、大臣はその場を後にした。
どうせ助からないと思ったのだろう。
事実、ミラの腹部からこぼれる出血は相当な量で、あと数分もしないうちに失血死してしまうだろう。
ミラは涙を流しながら、腹部に突き刺さった剣の刃を握り、引き抜いた。
その時に手の平を深く傷つけたが、痛みはほとんど感じなかった。それほどまでに、肉体が死に向かっているのだ。
「死ねない――まだ……」
そう自分に言い聞かせる。
Even達に事の真実を伝えなければ。
リースに謝らなければ。
最後に見たリリスの表情すら曖昧なまま死にたくないと、ミラは傷口を抑えながら地を這い……。
「すまぬな。遅くなった」
出血で意識が朦朧となりながら、聞き覚えのある声がした。
もう、ミラには顔を上げる力もない。
その誰か――提灯者モンはミラを仰向けに寝かせると、その傷口に手をかざした。
リリスとは違う温かみのある暖色の光がその手から漏れ、痛みが薄れる。
痛みに呻いた声が段々と柔らかくなり、同時に緊張の糸が切れてミラは意識を手放した。
「リリスの魔力が守ったか……あの愚か者め。死してなお、いったい何をする気じゃ」
モンは応急処置を施したミラを年老いた細腕で軽々と抱え、踵を鳴らした。
ただそれだけで簡単にエスタリアスリップの転移門を構成し、彼はその中に姿を消す。
後に残ったのは血まみれの剣と、大きな血だまりだけだった。
それからしばらくして、カイオス王が座する王城で鬨の声が上がった。
カイオス王Tabaiが反乱軍に討たれたのだ。
王都にはリリスの父親である前国王時代に使われていた貴族衣装を模した鎧をまとう兵士たちが雪崩込み、王城では王を討たれて混乱した兵士や騎士が反乱軍たちに追われ、殺され、王城から姿を消していく。
その中に、Even達の姿があった。
カイオス王国への到着と同時の敗北は若い彼らの精神を追い詰め、敗走を余儀なくさせた。
大臣がミラへ吹き込んだ通り、カイオス王国は混乱の坩堝と化した。
違うのは、それが『蒼の魔女』リリスが関わったのではなく、反乱軍が王殺しを成したという事。
そして、カイオス王国はこれから数年に渡る内乱に突入する。
反乱軍――いや、新しいカイオス王国の正規軍は新しい闇の血族……『蒼の魔女』リリスの弟にあたる少年を王に据え、悪政を敷く正規軍打倒を掲げた反乱軍は正統なる光の血族であるEvenを指揮官に据え――光と闇の血族は戦争という混沌の濁流に翻弄されていくことになる……。
そんなカイオス王国の惨状を感じながら、リリスは何もない荒れ地に横たわっていた。
まだ意識が残っているのは、彼女が魔女だったからか――それともこれは、魂が末期の光景を刻もうとしているからか。
自ら命を絶った後のことを、覚えていない。
……時代の混乱に翻弄される生徒達を憂い、ミラの無事を願い――少しずつ薄れていく自分の生命力に最期の時を悟る。
――生きて。
魔力に乗せた最後の言葉が、生徒たちに届いたかも確認できないまま、リリスはその意識を手放した。
直後、彼女の前に蒼い光――魔力が現れる。
横たわったまま微動だにしない肉体から溢れた膨大な量の魔力はリリスの前に集まり、一つの形となる。
綺麗な、宝石。
研磨されていない、自然の美しさを宿した暗闇よりもなお深い、蒼色のベリル。
その美しい宝石は、リリスの亡骸を癒すように、その胸の上で淡く輝き続けていた……。
<<前の章
|
次の章>>