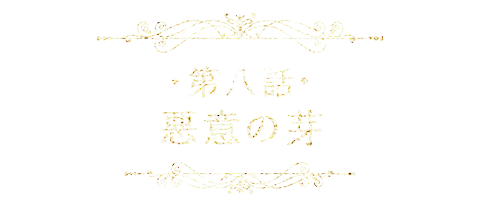
どれくらいの時間が経っただろうか。
リリスが羊皮紙にインクに浸した羽ペンを走らせていると、ドアがノックされた。
顔を上げる。
まず視界に映るのは太陽と月、そして七つのエスタリアで造られた天球儀だ。
鉄製のそれは部屋の中央に位置し、ゆっくりと動いている。
他にも何者か分からない人物の頭蓋や古ぼけた本、年代物の装飾品などなど。
長く使っている部屋だが掃除は隅々まで行き届いておらず、中には埃を被ったものまである。
木造の椅子に座りながら一瞬だけ室内を見渡したが、今更掃除をする暇もないことに気付く。
そもそも、この学長室を訪ねてくる生徒はおらず、訪ねる事が出来るのはリリスが呼んだ人物だけなのだから、取り繕っても意味がないと思って肩から力を抜いた。
「入りなさい」
「失礼いたします、リリス先生」
聞きなれた先生という言葉に、リリスは口元が緩むのを自覚する。
平和な証拠だ。
ふと、そう思う。
そう思いながら、もう一度リリスは手元に視線を落として羊皮紙に書き掛けの手紙に取り掛かった。
呼ばれたリースは、そんなリリスの対応を気にすることなく学長室へ足を踏み入れると、ゆっくりと室内を見回した。
まず気付くのは、掃除が行き届いていないこと。
すれ違いざまに天球儀をゆっくりと回しながら、続けて古ぼけた書物が乱雑に置かれた机を指でなぞる。
リースの白磁のような指先が埃で汚れた。
それを冷めた目で見ると、ため息を一つ。
壁際にある調度品が飾られた飾り棚も似たような状態で、ガラス戸が閉じられているので中身はまだ大丈夫だが、しかしその隅には汚れが目立つ。
この学校で一緒の時間を過ごすようになる以前のリリスを知っているリースだが、王城で暮らしていた頃はもう少し整理整頓が出来ていたような気がした。
それとも、城の家政婦が掃除を頑張っていただけなのか。
そんな昔に思いを馳せていると、手紙を書き終えたリリスがようやっと顔を上げてリースを見た。
「それで、今日はどのようなご用件でしょうか?」
「ええ――ミラの様子はどうかしら?」
珍しい、と。リースは思った。
リースが知るリリスという女性は何でも知り、そして魔力によって世界とつながり、この歴史上において最良の選択肢を選べる魔女と古き友人――提灯者モンから聞いていた。
そんな魔女が質問をしてくるなんて、と。
けれど、それは表情に出ない。
最良を選べるからと言って、悩みがないわけではないのだろう、と。
そして、彼女のその質問から何を悩んでいるのかというのは、おおよその見当がついていたからだ。
「皆と仲良くしています。明るく……人付き合いが苦手な私を気遣ってくれるくらいに」
「そう」
ただ一言だけを返して、しばらくの無言。
リリスは手の中に在る丸められた羊皮紙を両手で握りながら、心ここに在らずという様子で木造の椅子をギイ、と鳴らす。
リースもまた無言。
悩むリリスの傍に控え、何をするでもなくただ立ち尽くす。
それから数分の時間が流れて、ようやくリリスはゆっくりと深く息を吐いた。
「どうするべきかしら?」
「先生のお好きなように――私は、それで構いません」
リースは自分の意見を述べない。いや、リリスが選択した未来なら、どんな形であれついて行く覚悟があった。
最初は提灯者モンに導かれてリリスと出会ったが、今ではリリスの傍に居るのが当たり前になっている。
それは義務感や強制されたというわけではなく、リース本人がそれを望んでのこと。
もしリリスが破滅の道を選んでも、リースは文句を言うでもなく、ただ淡々とその隣に立つ――立ちたいと思う。
それは、リリスという魔女の魅力がそうさせるのではなく、最愛の兄を無くし、国を傷つけ、そしてこの欠片エリアまで逃げてきた――生徒たちに愛されながらも孤独な魔女の傍にいてあげたいという気持ち。
それに名前を付けるなら、他者はリースの気持ちをどう言葉にするだろう。
……そんなリースの内心を慮れず、リリスは机の引き出しを開けると、中から数枚の白紙を取り出した。
「ミラを呼んでちょうだい」
「すぐに?」
「ええ。読んでおいて申し訳ないけれど、あの子にも頼みごとを任せようと思うのだけど」
「とてもいい考えだと思います」
その言葉は本心。
リリスはミラに歩み寄る選択肢を選んだ。
ではミラは?
その答えを知る術を、リースは持たない。
リリスが持っていた羊皮紙に書かれた内容を聞かないまま、リースは学長室を後にする。
ただ、ふと横目に留まった手紙には、カイオス王国の刻印が刻まれていた。
・
時間は少しだけ戻り、ミラの自室。
それは、創造したミラ本人も、少しの間驚いて言葉が出なかったほどの奇跡。
エスタリアを繋ぐ門。
数度だけ見たことのある――リリスやモンといった熟練の魔女魔法使いだけが使えるはずの転移魔法。
それを、無意識にとはいえ、ミラは成功させていた。
彼女は躊躇いがちにその扉へ手を伸ばすと、ゆっくりと開く。
その先に見える光景は、見覚えのある――カイオス王国の中庭。
この欠片エリアへ来る直前までミラたちが居た場所だ。
少し記憶と違うのは、庭園にある花が手入れもされずに枯れてしまっていることだろう。
枯れた庭園、灰色の空、騒がしい王城。
見張りの兵士は立っておらず、窓から見える城内に人の姿はない。
なんと寂しい光景か――まるで世界の終末を切り取ったかのような扉の向こうの光景に、けれどミラは胸を痛めた。
「……寂しい景色」
ミラは迷わず、裸足のまま扉を抜けた。
カイオス王国――第三エスタリアの土を踏む。
欠片エリアとは違う、と思った。
そして、足裏に感じる地面の感触で自分が裸足だったことに思い至る。
戻ろうかと考えたが、ミラはそのまま数歩を踏み出す。
蒼の扉は消さない。一度閉じたらまたちゃんと魔法を使えるか不安だったからだ。
扉から顔を逸らし、厚い雲で陰った太陽を見上げる。
そして空気の流れを頬で感じ……意識が世界を渡ると、リリスとの繋がりが薄れたような気がした。
それを少しだけ寂しく、そして不安に思っていると――遠くから人の気配。
咄嗟にミラは身を隠そうとしたが、それより早く歩いてきた人物がミラに気付いた。
「おお、お前は……見覚えがあるぞ」
声をかけられて、ミラは戸惑った。
見覚えのない、まったく知らない人物だったからだ。
栗色の巻き毛に、煌びやかな衣服。
低い身長と出っ張った腹部に目が行き、汗や脂が浮いた顔に張りついたニヤケ顔がミラの顔を、そしてそこからゆっくりと降りて肢体を嘗め回すように見た。
それが気持ち悪くて、ミラは咄嗟に両手で体を隠すように動いてしまった。
幸いにも、蒼の扉は男の視界からは死角になっていて気付いていない。
「そうだ、お前は――リリス女王と一緒に城から消えた女だな」
「……どちら様でしょうか?」
好色な視線から逃げるように一歩下がると、男が間を詰めるように一歩前に出る。
「儂は――まあ、名は伏せておこう。その方がお互いのためだろう」
「は、はあ……」
「いくつか聞きたいのだが――リリス女王は城に戻られたのかな?」
「いえ、先生は……」
「先生?
彼女は今、どこかで教鞭をふるっておられるのかな?」
あ、と思った時には遅かった。
それで欠片エリアの存在に気付くほど聡くはないだろうが、なんとなく、この男にリリスのこと、自分の現状を知られるのは危険だとミラは直感する。
「それでは、失礼します」
ミラはすぐにこの場を離れようと背を向けて蒼の扉に向かって駆け出す。
飛び込んで扉を閉め、魔法を消せば気付かれないと思って――。
「ふむ……リリス女王のことで困ったら、儂を訪ねてきなさい。今はカイオス王国とオルダー公国の国境にある砦に居る……と言えば分かるかな。オルダーのお嬢さん」
国境の砦と言われて、ミラが思いつくのは一つだけだった。
リリスと初めて関わった場所。
彼女の軍が攻めてきて、母が深手を負った場所――。父はその争いで命を落とし、その日まで注がれていた両親の愛は消え、ミラは孤児になった。
ミラの足が一瞬止まった。けれどすぐに駆け出す。
ドクンドクンと、心臓が壊れてしまったように高鳴っていた。
ミラはすぐに蒼の扉に飛び込むと、魔法を解除。扉を消してしまう。
「……あの男」
話したのは一瞬。
会話とも言えないような短い内容だったのに――ミラは自分が何をしてしまったのか、そして何をしようとしたのかが分からなくなってベッドへ倒れこんだ。
まだ、心臓が高鳴っている。
リリスほどの魔女でなければなしえない単独移動を無事に終える事が出来たのは、奇跡としか言いようがないことだった。
そして、奇跡には代償が付きまとうというのが世の常である。
ミラのこの奇跡にも、当然のように代償が必要だった。
……ミラがもう一度……本人でも止めるべきだと思いながら、第三エスタリアへと移動したとき、ミラはまた身長が低い小太りの貴族と会ってしまった。
その場に立ったままなのは、またミラが現れると確信していたからか。
一度目が偶然なら、二度目は必然。
きっと、自分はこの男と出会う運命にあるのだろう――なぜか、そう思えた。
「おや、またお会いしましたな」
男が、口元を三日月のように歪めて笑った。
「儂は……まあ、今はもう存在しませんが、旧カイオス王に仕えていたものです……リリス女王とお会いすることは?」
「それは、できません……一つ、お聞きしても?」
「もちろんですとも。オルダー公国のお嬢さん……今はリリス女王の養子でしたか?」
「詳しいのですね」
「そうでしょうか?」
とぼけた口調で、小太りな外見からは想像もできない綺麗な所作で一礼。
ミラも男に倣ってスカートの裾をつまむと優雅に一礼をした。
「まだ、この国の内乱は続いているのですか?」
「もちろんですとも。二年前はリリス女王に敗れましたが、Tabai王が軍を指揮するようになってから、何とか持ち直す事が出来ました。今日は、Tabai王に城を明け渡すよう言いに来たのですが、断られてしまいました」
「……もう、そこまで」
「ええ。どうやら王には、心の支えがある様子――リリス女王という、切り札が」
厭な声だと、ミラは思った。
どこか相手を下に見ているような、内心を覗き込もうとしているような……今まで出会ったことのないタイプの人間。
ミラは警戒しながら、しかし今回は逃げない。
「お時間がある時に、是非お話を伺いたいですな」
「せん……リリス女王の、ですか?」
「ええ。貴方も、その為にまた儂の前に現れたのでは?
お母上の敵を討ちたいのでは?」
「――――っ」
「そう、その瞳は語っておられるように見えますが」
一度なら偶然、二度目は必然。
ミラはエスタリアスリップという奇跡を起こし、その代償は、すぐ目の前に。
どうして、と思う。
何故、と思う。
この男は……どこか信用できない。
今も浮かべている笑顔には裏があると、人付き合いの経験が少ないミラでも分かる。
それでも、まだ燻って、残っているのだ。
母親が死んだときの、血の匂い。冷たくなっていく手の感触。
そして、死の原因となった――争いを起こした人物が何者かを、まだ覚えている。
リリスが邪魔な貴族と、リリスを憎み、それと同じだけ愛しているミラの出会いは、やはり必然だった。
この男との関係は、これから先、長い間続いていく。
そう、確信がミラの胸の奥にあった。
――その確信は正しく。
――平穏な学校生活を送りながら男との密会を続け……それは、この日から三年もの間、続くことになる。
<<前の章
|
次の章>>